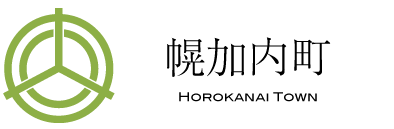国民健康保険税とは
国民健康保険税とは、皆さんが病院にかかった時など、国民健康保険事業の健全な運営を確保するために充てられる税金です。
保険税の納税義務者
国民健康保険に加入している世帯の世帯主に対して課税されるため、社会保険や後期高齢者医療保険に加入している世帯員については課税の対象になりません。
保険税の決め方と税率
国保税は地方税法に基づき、医療給付分、後期高齢者支援金分、介護納付分の3つの課税額により構成されており、各課税額を所得割、均等割、平等割の要素から算定を行う3方式を採用し、条例により税額・税率を定めています。
なお、それぞれの計算料率は、毎年6月に決定します。
| 医療分 | 支援分 | 介護分 | 課税の基礎 | |
| 所得割 | 4.42% | 1.04% | 1.05% | 加入者全員の前年所得より算出 |
| 均等割 | 20,000円 | 5,600円 | 5,200円 | 1人あたり |
| 平等割 | 22,000円 | 6,400円 | 4,400円 | 1世帯あたり |
| 課税限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 |
※令和3年度より「資産割額」は廃止しました。
保険税の計算方法
令和7年度の保険税は次の方法で世帯ごとに計算します。
1.医療給付分保険税
74歳以下の方の医療費に充てる分です。
次の(1)~(3)を合算した額が、1年間の医療分保険税になります。
| (1)所得割額 | 令和6年中の所得(※注1)-43万円×4.42% |
| (2)均等割額 | 20,000円×加入者数 |
| (3)平等割額 | 22,000円(一世帯あたり) |
| (1)+(2)+(3)の合算額=1年間の医療分保険税 |
|
※世帯の所得割額は、各加入者ごとに計算した所得割の合計額となります。
※最高限度額は660,000円です。
|
※注1
|
2.後期高齢者支援金分保険税
後期高齢者医療制度の加入者の医療費に充てる分です。
次の(1)~(3)を合算した額が、1年間の支援金分保険税になります。
| (1)所得割額 | 令和6年中の所得(※注1)-43万円×1.04% |
| (2)均等割額 | 5,600円×加入者数 |
| (3)平等割額 | 6,400円(一世帯あたり) |
| (1)+(2)+(3)の合算額=1年間の支援金分保険税 |
|
※世帯の所得割額は、各加入者ごとに計算した所得割の合計額となります。
※最高限度額は260,000円です。
|
※注1
|
3.介護納付分保険税
介護費に充てる分です。
世帯内の国保加入者の中に、40歳以上64歳以下の方がいる場合は、次の(1)~(3)を合算した額が、1年間の介護分保険税になります。
該当者がいない場合はかかりません。
| (1)所得割額 | 令和6年中の所得(※注1)-43万円×1.05% |
| (2)均等割額 | 5,200円×加入者数 |
| (3)平等割額 | 4,400円(一世帯あたり) |
| (1)+(2)+(3)の合算額=1年間の介護分分保険税 |
|
※世帯の所得割額は、各加入者ごとに計算した所得割の合計額となります。
※最高限度額は170,000円です。
年度の途中で40歳になる方の介護分保険税について
|
|
※注1
|
保険税の月割計算
年度の途中で加入・脱退された方の保険税
国民健康保険税は、4月1日現在の加入者に1年分(4月分から翌年3月分までの12ヶ月分)が課税されます。
ただし、年度の途中で加入した場合は加入した月から、脱退した場合は脱退した月の前月まで、月割して計算されます。
保険税に変更があったとき
加入・脱退により保険税額が変更となった場合、変更日以降に到来する納期にて、1期あたりに納付して頂く保険税を調整します。
なお、すでに納められた保険税が変更後の年間保険税額より多い場合(保険税が減額となる場合)は、多く納められた分を、後日お返し(還付)します。
保険税の軽減
所得が一定額よりも少ない世帯に対して、国保税を軽減する制度があります。国保税のうち均等割額と平等割額を軽減するもので、医療給付分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分それぞれに適用されます。
軽減の判定基準につきましては、下表のようになっております。
令和7年度の場合
| 令和6年中の所得(※注1)が下記の金額以下の世帯 | 減額割合 |
| 43万円+(給与年金所得者数-1)×10万円 | 7割軽減 |
| 43万円+(給与年金所得者数-1)×10万円+(28万5千円×加入者数) | 5割軽減 |
| 43万円+(給与年金所得者数-1)×10万円+(52万円×加入者数) | 2割軽減 |
※注1
|
適用要件について
所得の申告(確定申告、住民税の申告、国保の所得申告のうちいずれか)がお済みである必要があります。
保険税の納付方法
納税通知書の発送
国民健康保険税の納税通知書は、毎年7月にお送りします。通常4月から翌年3月までの12ヶ月分の保険税を、7月から翌年2月までの4回で納めていただきます。
年度の途中で加入した方は、届出月により納付回数が異なります。
納期限
| 期別 | 納付期限 |
| 第1期分 | 7月末 |
| 第2期分 | 9月末 |
| 第3期分 | 11月末 |
| 第4期分 | 2月末 |
※詳細な期日については、7月に送付した納税通知書もしくは納付書をご確認願います。
※納期限が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納期限になります。
納付方法
・納付書
下記の金融機関、幌加内町役場、役場朱鞠内支所で納付できます。
※北空知信用金庫、きたそらち農業協同組合、ゆうちょ銀行等。
詳しくは、最寄りの金融機関へお問合せください。
・口座振替
納税通知書と通帳、通帳届出印を用意して、下記の金融機関へお申し込みください。
※北空知信用金庫、きたそらち農業協同組合、ゆうちょ銀行等。
お問い合わせ先
住民課 税務係
- 電話:0165-35-2124
- FAX:0165-35-2127